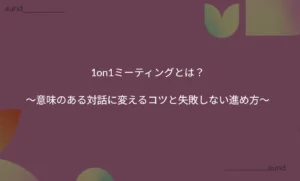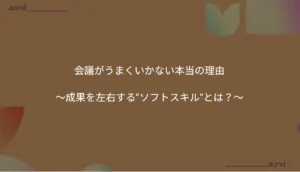OKRの真価を引き出す方法とは? 戦略指針会議で目標を組織の行動に変える実践フレーム

OKRの真価を引き出す方法とは?
~ 戦略指針会議で目標を組織の行動に変える実践フレーム~
目次
1.OKRとは?
2.OKRとKPIとの違いとは?
3.なぜOKRはうまく機能しないのか?
4.OKRと連動すべき「戦略指針会議」とは?
5.OKR × 戦略会議の実践フロー
6.まとめとaundのアプローチ
1. OKRとは?
1-1. OKRの定義と目的:なぜ今OKRが注目されているのか?
OKR(Objectives and Key Results)とは、組織の目標(Objective)と、成果を測るための主要な結果(Key Results)をセットで設定する目標管理手法です。シンプルで柔軟性が高く、組織の方向性と個々人の行動を明確に接続することで、組織全体の一体感を生み出す特徴があります。
特に注目される理由は、「変化の激しい時代に適応できる仕組み」である点です。旧来の年次KPIとは異なり、OKRは四半期単位で柔軟に見直され、組織全体をアジャイルに動かすための「エンジン」として活用されます。
さらに、OKRは単なる目標管理のフレームワークにとどまらず、「組織文化」そのものを変える力を持ちます。部門や役職を超えて目標が可視化・共有されることで、サイロ構造が崩れ、心理的安全性のあるフラットな組織づくりが進むのです。
1-2. OKRの起源:インテルのアンドリュー・グローブと「マネジメント・バイ・オブジェクティブ(MBO)」
OKRのルーツは、アメリカの半導体企業インテルに遡ります。インテルの元CEOであるアンドリュー・グローブは、ドラッカーの提唱した「MBO(目標による管理)」に実務レベルでの限界を感じ、より実行力のある形でOKRを生み出しました。
彼は、組織の成長には“全員が自律的に動けるようになること”が不可欠だと考え、OKRを通じて組織全体が共通の目標に向かって動ける構造をつくったのです。OKRは「目標設定」と「行動の明確化」をセットで捉えるため、行動変革に直結するという点で、MBOの進化形といえるでしょう。

1-3. 世界の企業が採用するOKR:Google・Meta・Netflixの事例
OKRが世界的に広まるきっかけをつくったのは、1999年にインテル出身のジョン・ドーア(John Doerr)がGoogleにOKRを紹介したことです。
以来、GoogleではOKRを中核に据えた目標管理を20年以上継続しており、同様にMeta(旧Facebook)、LinkedIn、Netflixなど、アジャイルでイノベーティブな企業が次々に導入しています。
たとえばMetaでは、四半期ごとにOKRを設定し、チームごとに進捗を定期的にレビューするプロセスを組み込んでいます。Netflixでは、OKRを通じて「挑戦する文化」を醸成し、創造性の高い成果を支える土台としています。
これらの企業に共通するのは、「目標を管理する」のではなく、「目標を通じて文化と行動を変革する」という姿勢です。
1-4. GoogleはOKRをどう運用しているのか?
Googleでは、OKRは全社員が四半期ごとに設定し、社内ですべてが公開されるのが原則です。経営陣のOKRも含め、誰もが自分以外の目標を見ることができるようになっており、透明性とオーナーシップを生み出す仕組みになっています。
重要なのは、GoogleにおけるOKRは「達成率が60~70%でちょうどよい」とされていることです。これは、「あえて高い目標を掲げることで、創造的な挑戦が生まれる」という文化に基づいています。全力で挑戦して届かない目標こそが、組織の限界を押し広げるのです。
【引用】“We do not expect everyone to hit all of their OKRs. If they do, the goals weren’t ambitious enough.” – John Doerr, Measure What Matters
出典元リンク(英語)
OKRの導入を通じて、Googleは単に目標管理を効率化するのではなく、組織の思考様式と行動パターンを変革することに成功しました。
1-5. 実際のOKRの運用方法:どう運用すれば成果につながるのか?
OKRは、ただ設定するだけでは意味を成しません。実際の運用において重要なのは、「どのようなサイクルで、どのように目標を設計・実行・見直すのか」です。ここでは一般的な企業におけるOKRの運用方法の流れを紹介します。

ステップ①:四半期ごとに設定
OKRは通常、四半期単位で設定されます。これは、年単位の目標よりも機動力があり、チームや市場の変化に柔軟に対応できるからです。
- Objective(目標):チームや個人が目指すべきインパクトのある状態を、1~3件程度設定
- Key Results(成果指標):Objectiveに対して、成果を測定できる具体的な指標を3~5件程度設定
Objectiveは定性的に、Key Resultsは定量的に記述するのが基本です。
ステップ②:目標の共有と調整
OKRは「透明性」が命です。チームや全社レベルで目標を「見える化」し、他部署との連携や依存関係をあらかじめ確認します。
Googleなどでは、OKRを社内全体に公開することで、上下左右の連携が取りやすくなり、サイロ化(縦割りの弊害)を防いでいます。
ステップ③:定期的なチェックイン(週次 or 隔週)
OKRは「立てたら終わり」ではなく、定期的に進捗を確認するミーティングが不可欠です。
- 進捗率を確認(例:0.0〜1.0で自己評価)
- ボトルネックの共有
- 次週の重点タスクのすり合わせ
- KRの妥当性の再確認
ここでの目的は「進捗の監視」ではなく、建設的な対話を通じて、目標への前進を加速させることにあります。
ステップ④:四半期末のレビューと次期へのフィードバック
四半期の終わりには、OKRレビューを実施します。達成率の高さではなく、そこから得た「学び」を重視します。
- 達成率60〜70%が理想(ムーンショット型目標であるため)
- 達成/未達問わず、良かった点と改善点を振り返る
- 次期OKRに活かすフィードバックを得る
このレビューを繰り返すことで、チームは「成果を生む目標の立て方」「振り返る習慣」を組織文化として育てていくことができます。
2. OKRとKPIとの違いとは?
2-1. 混同されがちな「OKR」と「KPI」
組織で目標管理の話になると、しばしば「OKR」と「KPI(Key Performance Indicator)」が同じような文脈で語られます。しかし、この2つは似て非なるものです。
KPIは、すでに設定されたゴールに対して「どれくらい達成しているか?」をモニタリングするための指標です。一方、OKRは「どこに向かい、どう変化していくか?」を定める未来志向の目標設計フレームワークです。
簡単に言えば、KPIは「健康診断」、OKRは「トレーニングメニュー」に近い存在といえるかもしれません。現状を測定するKPIと、未来の成長に向けて設計するOKRは、用途が根本的に異なるのです。
もちろんOKRの中でもKPI的な観点で、プロセスを測ることはありますが、根本の考えは違うということをとらえておいてください。
2-2. 決定的な3つの違い
| 観点 | OKR | KPI |
|---|---|---|
| 目的 | 組織やチームの挑戦的な成長と変革 | 現在のパフォーマンスの維持・管理 |
| 性質 | 目標と成果の設計(未来志向) | 実績の評価と改善(過去志向) |
| 達成基準 | 完全達成しないことが前提(60~70%でもOK) | 100%達成が理想・前提 |
OKRは「大胆な目標を設定し、現状を突破するための起爆剤」です。一方で、KPIは「今やっていることを正しく遂行しているか」をチェックするための体温計のようなもの。
両者は対立する概念ではなく、補完し合う存在です。
2-3. OKRとKPIをどう使い分けるべきか?
理想的な運用では、「KPIで日常の健康を保ち、OKRで未来への挑戦を設計する」というバランスが重要です。
たとえば、営業部門において:
- KPI → 月の商談件数や受注率(=現在の健康状態)
- OKR → 新しい業界へのアプローチや、新規提案フローの開発(=未来への挑戦)
KPIだけでは、既存の枠内での最適化にとどまりがちです。そこにOKRを加えることで、現状の「正解」を超える取り組みが生まれます。
2-4. 日本企業でありがちな誤解
日本企業では、KPIが目標管理の“すべて”になっているケースが非常に多く見られます。特に年次の目標管理制度では、100%達成が重視され、挑戦的な目標は「リスク」として敬遠されがちです。
OKRを導入する意義は、そうした守りの文化を破り、挑戦を文化に変えるところにあります。たとえ60%の達成でも、「この挑戦があったから変われた」と実感できる目標設計こそが、OKRの真価なのです。
✅ OKRは「できそう」なことではなく、「やりきったらすごい」と思えることを設定する。
✅ KPIは、挑戦を支える「モニタリングの装置」として併用する。
3. なぜOKRはうまく機能しないのか?
3-1. OKRは「導入すれば成果が出る」魔法のツールではない
OKRは、GoogleやMetaの成功事例が先行して語られることが多く、表面的に「すごそう」「先進的」といったイメージだけで導入されてしまうケースも少なくありません。しかし、実際には多くの企業で「うまく機能しなかった」「結局、形骸化した」といった声も聞かれます。
なぜ、OKRはうまくいかないのでしょうか?
3-2. よくある失敗要因
(1)上から押しつけられた目標設定
OKRの本質は「チームや個人が自発的に、組織のビジョンに沿って挑戦的な目標を掲げること」にあります。しかし、実際の現場では、経営層が一方的にOKRを設定し、現場が受け身になる構図がよく見られます。
その結果、メンバーは「これはKPIの言い換えにすぎない」と感じ、主体性を失い、モチベーションも上がりません。
(2)“挑戦的すぎる”か“現実的すぎる”目標設定
OKRは60~70%達成が理想とされる「ムーンショット」的な目標を良しとしますが、そのバランス感覚を掴めていない企業が多くあります。
- 現実離れした目標 → 意欲を削ぐ
- 達成前提の目標 → 意味がない
つまり、「絶妙に難しいけど頑張れば届きそう」なラインの設定ができていないのです。
(3)Key Resultsが単なるToDoになっている
Objective(目標)を掲げたものの、Key Results(成果指標)が「行動予定」や「実施済タスク」になってしまうケースは少なくありません。
例:
- ❌「週に3回営業先を訪問する」← 行動であり成果ではない
- ✅「〇〇業界で10社の新規商談を獲得する」← 成果指標
Key Resultsは、「何を達成したか」を定量的に測れる形で表現する必要があります。
(4)レビューされない/振り返られない
OKRは、継続的な対話と振り返りがなければ意味がありません。
にもかかわらず、設定したまま放置され、四半期の終わりに思い出したように見直す──そんな状態では、OKRはただの飾りにすぎません。
3-3. 組織文化との不一致
日本企業においては、特に以下のような文化的背景がOKRの機能を妨げることがあります:
- 失敗を許容しにくい風土:「達成率が低い=評価が下がる」という発想
- 上意下達の構造:「自分で目標を決める文化」が定着していない
- 年次評価との矛盾:人事制度とOKRの方向性が噛み合っていない
これらの要素があると、OKRは“挑戦”の道具ではなく、“管理”の道具として扱われ、目的と手段が逆転してしまいます。
3-4. OKRを文化として根づかせるには?
うまく機能しない要因を避けるためには、OKRを「制度」ではなく「対話の文化」として捉える視点が必要です。
- 目標設定にチーム全体を巻き込む
- Key Resultsに成果とインパクトを反映させる
- 定期的な「レビュー・振り返り」の場を設ける
- 失敗に寛容なマインドセットを育てる
OKRは、単なる目標管理の仕組みではありません。「どうすれば、組織全体で“変化”に向かって動き続けられるか?」という問いへの、実践的な答え方の一つなのです。
4. OKRと連動すべき「戦略指針会議」とは?
OKRをうまく運用する組織には、ある共通点があります。それは、四半期に一度「戦略指針会議」を行っているということです。
この会議は、単なる進捗確認や方針説明の場ではありません。次の3〜6ヶ月の組織全体の方向性を再定義し、変化への適応力を持つ「しなやかな組織」をつくるための戦略会議です。
4-1. なぜ戦略指針会議がOKRと連動すべきなのか?
OKRが「目指すべき目的と成果を言語化するフレームワーク」であるならば、戦略指針会議はそれを“全社的な行動”に落とし込む実践の場です。
- OKRで掲げたObjective(目的)が、現場の行動にまで落ちていない
- 立てたKR(成果指標)に対して、なぜ達成できなかったかの本質的な検討ができていない
- 市場や環境の変化により、当初立てたOKRの前提条件がすでに崩れている
こうした課題を補完し、戦略・実行・改善のサイクルを確実に回すのが戦略指針会議の役割です。
4-2. 戦略指針会議の進め方(8ステップ)
- ポジティブスタート
会議の冒頭は、過去3ヶ月の「成功体験」から共有。成功したことを可視化し、組織のポジティブな流れを強調することで、会議全体に前向きな空気をつくります。 - 会議の目的とゴールを明確にする
「この会議で何を決めるのか」「何を持ち帰るのか」を冒頭で定義します。ゴールなき会議は、OKRとも連動しません。 - 問題と課題の棚卸し
現在の組織が抱える課題をメンバー全員が共有。重要なのは、課題を“愚痴”で終わらせず、「どうすれば解決できるか?」という言葉に変換することです。 - 言いづらい課題をあえて出す
普段は語られにくい組織の根深い問題(例:リーダーシップの欠如、評価制度の不透明さなど)を、あえてオープンに議論。チームの心理的安全性を育てるきっかけにもなります。 - 6〜12ヶ月後のOKRに基づいたゴール設定
- 例:「12月末までに新規顧客を20社獲得」
- OKRで設定したObjectiveに対して、KRを会議内で再検討し、次の四半期の指針として練り直します。
- 重点戦略領域(ストラテジックフォーカス)の設定
メンバーそれぞれが「この数ヶ月で自分が最も貢献できる分野」を出し合い、全体で絞り込んで明確に設定します。OKRと照らし合わせながら、フォーカス領域を整合させていきます。 - コミットメントの明確化
各メンバーが「この四半期で必ず達成する行動目標」を宣言。たとえば「4月中に◯◯の提案を完了」など。これをチーム全体で共有し、コミットメントシートとして記録します。 - 1ヶ月以内のインパクトアクションを設定
戦略は行動に落とし込まれてこそ意味があります。会議の最後には、1ヶ月以内に実行するアクションを全員で設定し、「行動から始まる成果づくり」の意識を高めます。
4-3. 戦略指針会議 × OKRで加速する組織づくり
このように、戦略指針会議はOKRを「掲げただけ」で終わらせず、メンバー一人ひとりのアクションにまでつなげる“翻訳の場”として機能します。
また、変化の早い市場においては、OKRを設定する前提自体が変わってしまうこともしばしばあります。そんなとき、「ピボット」の必要性をチームで議論する場としても、戦略指針会議は極めて有効です。
変化に適応しながらも、組織としての一貫性を保つ。
そのための「柔軟な軸」となるのが、OKRと戦略指針会議の連動です。
5. OKR × 戦略会議の実践フロー
「OKRを設定したけど、現場に定着しない」「戦略会議はしているけれど、翌日からの行動が変わらない」——。多くの企業が陥るこのギャップを埋めるのが、「OKR」と「戦略指針会議」を一体で運用する実践フローです。
ここでは、組織全体の行動と成長を加速するための流れを、4つのフェーズに分けて解説します。
5-1. 戦略指針会議(四半期頭)で「OKRの設計」と「意思統一」を行う
四半期のスタートには、チームや部署ごとの戦略指針会議を実施します。ここでの目的は、OKRを設定し、それが組織全体の目標と整合しているかを確認することです。
- OKR設計のポイント:
- Objective(目的)には「意味」と「志」を込める
- Key Results(成果指標)は具体的かつ測定可能にする
- 部署間・チーム間の整合性も必ず確認する(縦だけでなく横の連動)
OKRは、トップダウンではなく、「ダイアログを通じてつくる」ことが重要です。会議内でしっかり対話を行いましょう。
5-2. 月次でマイクロレビュー(ライトレビュー)を実施し、柔軟な調整を行う
OKRは四半期単位で運用されるものですが、月次での進捗レビューを挟むことで、柔軟な軌道修正が可能になります。
- マイクロレビューの構成:
- KRごとの進捗率を確認(定量データが望ましい)
- 障害となっている要因を明文化し、共有する
- Try(改善の試み)を明示する
このタイミングで、OKRがずれていないか?ピボットの兆候があるか?を意識的に振り返ることが大切です。
5-3. 1on1で個人の行動とOKRを接続する
OKRの浸透度を高めるには、マネージャーと部下の1on1で、個人の業務目標とOKRのリンクを確認することが有効です。
- 「このKRに対して、あなたが担えることは何か?」
- 「達成のために、どんな支援が必要か?」
- 「この目標に対する、あなたのやりがいは何か?」
個人と組織のゴールが重なったとき、OKRは真のドライバーとして機能します。
5-4. 四半期末の「戦略振り返り会議」で学習とピボットを仕掛ける
四半期末には、OKRの達成度をレビューしつつ、次のクオーターに向けた戦略再考を行います。
- 達成できたKRとその要因、できなかったKRとその背景を整理
- 市場や顧客、社内の変化に対する「仮説の更新」
- 必要であれば、Objectiveの方向性自体の見直し(ピボット)も検討
このとき重要なのは、「責任追及」ではなく「組織の学習」に軸を置くことです。そうでなければ、OKRは恐怖の評価指標となり、形骸化してしまいます。
参考記事:「KPTミーティングとは?成果を引き出す効果的な振り返りの方法と活用術」
5-5. OKR × 戦略会議の実践が生む「組織の変化」
この一連の流れを定着させることで、組織には次のような変化が生まれます。
- メンバー一人ひとりの行動が、戦略とリンクし始める
- ピボットを恐れず、変化にしなやかに対応できるようになる
- 会議の質が変わり、対話が活性化される
- 短期成果と中長期視点が、同時に組織の中に存在するようになる
OKRと戦略指針会議は、それぞれが組織変革の起点であり、連動させることで本当の「行動変革」が始まるのです。
6.まとめとaundのアプローチ
OKRと戦略指針会議を“生きた”仕組みにするために
OKRは、組織が戦略的に成長していくうえで非常に有効なフレームワークです。しかし、それが本当に力を発揮するためには、「会議」の質と組織全体の巻き込みが必要不可欠です。
OKRはただ“設定するもの”ではありません。それを組織のすみずみにまで浸透させ、メンバー一人ひとりのアクションに落とし込んでいくためには、対話・共創・振り返りといった“プロセス設計”が求められます。まさにここに、ファシリテーターの役割があります。
ファシリテーターが果たす役割とは?
ファシリテーターは、単なる会議の進行役ではありません。OKRや戦略指針会議の場において、以下のような“価値の媒介者”として機能します。
- 組織全体の視座を引き上げ、OKRの目的と意義を浸透させる
- メンバーの対話を促進し、隠れた課題や言語化されていない不安を引き出す
- 会議設計そのものを再構築し、行動変容を生み出す設計を施す
- 「戦略会議が戦略会議として機能する」ように土壌を整える
OKRのような抽象度の高い目標設定や、ピボットを含む判断には、「正解を出すこと」よりも「納得解にたどり着くプロセス」が重要です。このプロセスを支え、組織の中に対話の文化を育む存在こそがファシリテーターです。
aundのアプローチ
aundでは、OKR導入や戦略会議の設計において、ファシリテーション視点から組織に伴走しています。単に“研修”や“ツール導入”にとどまらず、実際の会議現場やチームに入り込み、以下のような支援を行っています:
- OKR設計支援(ObjectiveとKey Resultsの言語化、上位方針との整合)
- 戦略会議のファシリテーション(目的設計・会議の構成・対話の仕掛け)
- 会議の定例化支援(クオーターごとの振り返りと方針策定の習慣化)
- マネージャー層へのファシリテーション・コーチング
私たちの役割は、組織の中で「考えること」「向き合うこと」「決めること」を促進する土台をつくることです。制度や仕組みをつくることと同時に、そこで働く“人の意志”をいかに活性化させられるか。そこに、本当の意味での組織の成長があると考えています。
ご興味がある方へ
OKRの設計から、実際の戦略会議のファシリテーション、会議設計まで、aundでは柔軟にサポートを提供しています。
▶ 詳細はこちらをご覧ください
会議設計・ファシリテーション支援サービス - aund.jp
組織の可能性は、「一人ひとりの対話」から拓かれます。OKRを“仕組み”としてだけでなく、“文化”として根づかせる第一歩を、私たちと一緒に始めてみませんか?