1on1ミーティングとは?意味のある対話に変えるコツと失敗しない進め方
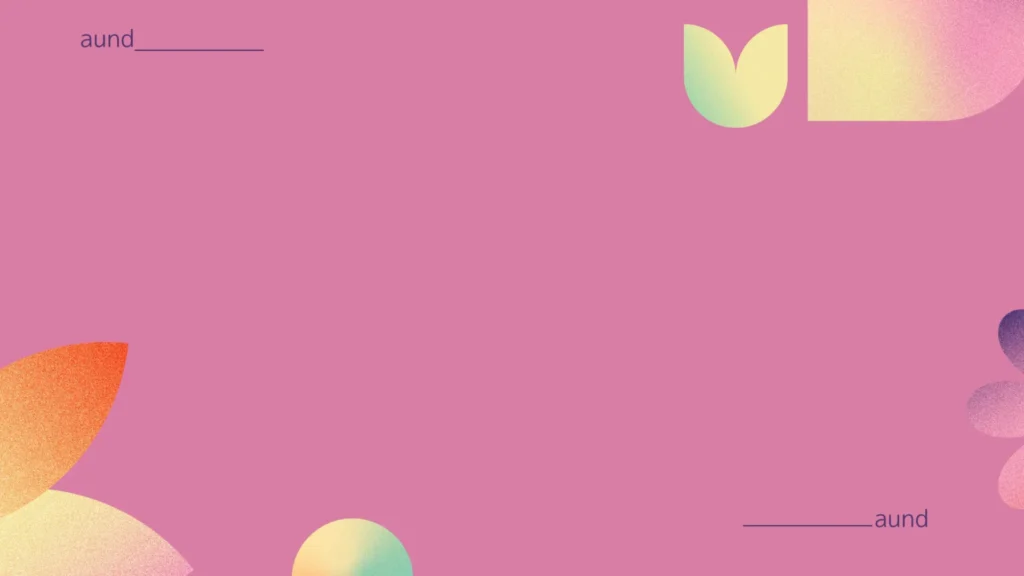
1on1ミーティングとは?
~意味のある対話に変えるコツと失敗しない進め方~
目次
1.1on1ミーティングとは何か?
2.形だけの1on1が生む問題
3.1on1ミーティングを機能させるための原則
4.1on1ミーティングの進め方(実践ガイド)
5.1on1ミーティングの本質的な効果とは?
6.aundのファシリテーターがサポートする1on1の可能性
1. 1on1ミーティングとは何か?
1-1. 部下の「本音」を引き出す、対話のための時間
「うちの1on1、ただの業務報告で終わってしまっている」
そんな悩みを抱えているマネージャーは、決して少なくありません。近年、多くの企業で取り入れられている1on1ミーティングですが、その本質が見失われている現場も少なくないのが現状です。
1on1ミーティングとは、マネージャーと部下が定期的に行う“成長のための対話の場”。
業務進捗を確認するだけの場ではなく、部下の価値観や感情、モチベーションの源泉に耳を傾け、支援することが目的です。
もともとはシリコンバレーのIntel社が1980年代に導入し、その後GoogleやFacebookなどのテック企業を中心に広まりました。日本でもヤフー株式会社がいち早く導入したことで注目を集め、現在では多くの企業が「組織開発」や「離職防止」の観点から採用しています。
とはいえ、形式的に実施するだけでは、逆に信頼関係を損なうリスクもあるのです。
1-2. 1on1の「本来の目的」と、ありがちな誤解
1on1は、単なる“上司と部下の面談”ではありません。最大の目的は、部下が「この人には安心して話せる」と感じられる関係性を築くことです。
にもかかわらず、ありがちな誤解として次のようなケースが見受けられます:
- 上司が一方的に話してしまう
- アジェンダが「業務報告」しかない
- フィードバックが評価や指導に偏ってしまう
- 形だけの月次面談になっている
こうした1on1では、部下は本音を語ることができず、やがて「意味がない」「やらされ感だけが残る」ものになってしまいます。
1on1の価値は「信頼関係づくり」と「成長支援」にあるという原点に立ち返る必要があります。部下が自分の考えや感情を安心して言葉にできる。それが、成果に直結する対話の第一歩なのです。
次章では、こうした「形だけの1on1」がなぜ起こるのか、どんな問題を引き起こすのかを詳しく見ていきましょう。
参考:「「アジェンダ × グランドルール」で会議の質を劇的改善!?少しの工夫で最大の効果を実感!」
2. 形だけの1on1が生む問題
2-1. よくあるNGパターン
「一応やってますよ、1on1。でも正直、ただの作業になっていて…」
これは、多くの現場で聞こえてくるマネージャーの本音です。
導入こそされたものの、「形だけの1on1」が蔓延すると、かえって部下との信頼を損ねたり、時間の浪費になってしまうことさえあります。以下のようなNGパターンは、特に注意が必要です:
- 業務報告だけで終わってしまう
→ 上司が「で、進捗どう?」と聞くだけになり、会話が広がらない。 - 一方的なアドバイスや説教になる
→ 対話ではなく「指導の場」になると、部下は身構えて本音を話せなくなる。 - アジェンダが曖昧で、何を話せばいいのか不明
→ 結果、形式的な雑談で時間を埋めるだけになってしまう。 - 記録も振り返りもない
→ 話した内容が活用されず、「この時間、意味あった?」と感じさせてしまう。
こうした状況が続けば、部下にとって1on1は「避けたい時間」になります。逆に、マネージャー自身も「やってるけど効果を感じない」と感じてしまい、徐々に対話の質が落ちていくのです。
2-2. なぜ「ただの業務確認」になってしまうのか
形骸化する1on1の背景には、いくつかの根本的な誤解や構造的な要因があります。
■「目的」の共有が不十分
多くの現場では、「1on1はやるもの」という形だけが独り歩きし、そもそもなぜやるのか、どんな価値があるのかが明確にされていません。マネージャーも部下も「決まってるからやってる」だけでは、効果的な対話にはつながりません。
■マネージャー側のスキル不足
1on1は、上司にとっても「傾聴力」や「問いかけの力」が求められる高度なコミュニケーションの場です。しかし、研修やトレーニングが不十分なまま形式的に導入されているケースも多く、マネージャーが戸惑ってしまうのも無理はありません。
■時間がとれない・優先度が低くなる
忙しい現場では、「会議と会議の合間に10分だけ」「今日は流してもいいか」といった扱いをされやすいのが1on1。結果的に、その重要性がチーム内で軽視されてしまうのです。
1on1が本来果たすべき機能は、信頼の構築、成長支援、エンゲージメントの強化です。
しかし、それが「業務確認の延長」になってしまえば、逆にモチベーションを下げる結果にもなりかねません。
3. 1on1ミーティングを機能させるための原則
3-1. 心理的安全性がすべての土台になる
1on1ミーティングの成否を決めるのは、会話の「中身」ではなく、まず「空気感」です。
どれだけ正しい問いを投げかけても、部下が「本音を話せない」と感じていたら、それは独り言に終わってしまいます。
ここで必要なのが、心理的安全性の確保です。
これは、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱した概念で、Googleが行った「効果的なチームに関する研究(プロジェクト・アリストテレス)」でも、最重要要素として挙げられています。
心理的安全性がある1on1では、部下がこう感じています:
- 「失敗しても怒られない」
- 「思ったことを率直に言っていい」
- 「自分の意見を持っていても尊重される」
つまり、「話すこと」自体がストレスにならないこと。
これは、上司のちょっとした相づちや、日頃の言葉遣い、感情の出し方すべてに影響されます。
3-2. マネージャーは「支援者」であり、主役は部下
1on1の場では、マネージャーが主導権を握ってしまいがちです。
しかし、本来この時間の主役は部下であり、マネージャーの役割は“答えを与える人”ではなく、“考えるきっかけをつくる人”であるべきです。
そのために必要なのは、「教える」ではなく「引き出す」姿勢です。
❌ NG例
「今度の案件はこうやって進めよう」「この部分は改善してくれ」
✅ よくある好例
「今回どう感じた?」「どこに一番難しさを感じた?」
「今の状態を10点満点でつけるとしたら、何点?その理由は?」
部下に「考えていい」「感じていい」「選んでいい」と思わせる問いかけが、関係性の質を高め、行動変容のきっかけになります。
3-3. 対話の“質”は準備で決まる
1on1が機能しない要因の一つは、準備不足による“流れ任せ”の対話です。
なんとなく集まり、なんとなく話して、なんとなく終わる——
この積み重ねでは、信頼関係も成長も生まれません。
効果的な1on1のために、マネージャー側が最低限準備すべきは以下の2点です:
- 部下に考えておいてほしいテーマを事前に共有する
例:「今、気になっていること」「最近、自分が誇れること」「仕事に関する不安」 - これまでの対話の記録やメモを振り返っておく
前回何を話したのか、どんな変化があったのかを覚えていることが、信頼のベースになります。
加えて、話しやすい「場づくり」も欠かせません。
カフェや会議室、オンラインでも「いつものミーティング」と違う空気を作ることで、1on1はより意味のある時間になります。
4. 1on1ミーティングの進め方(実践ガイド)
「よし、1on1をちゃんとやろう」と決意しても、「どう始めて、どう終わればいいの?」という声は少なくありません。
ここでは、1on1ミーティングを“ただの雑談”から“成長の場”に変える具体的な進め方を、ステップごとに解説します。

4-1. ステップ① 雰囲気づくりと関係性のウォームアップ
1on1は、始まった瞬間から「成長を促す会話」が始まるわけではありません。
まずは、関係性を温める“アイスブレイク”が大切です。
- 最近のプライベートで嬉しかったこと
- オフの時間の過ごし方
- ちょっとした雑談や笑い
こうしたやり取りが、部下に「ここでは安心して話せる」と思わせる“空気”をつくります。
ポイントは、話題を強制しないこと。部下の性格に合わせて温度感を調整しましょう。
4-2. ステップ② 自由な話題から内面を引き出す
形式的に「何か話したいことある?」と聞いても、答えが返ってこないこともあります。
そんなときは、思考や感情を自然に引き出す問いかけが有効です。
- 「最近、自分で『うまくいったな』と感じたことある?」
- 「今、ちょっとだけ気になっていることってある?」
- 「今週の仕事を10点満点で点をつけるとしたら?」
こうした問いは、評価や詮索ではなく、「考えるきっかけ」として機能します。
ときには沈黙があっても問題ありません。焦らず、相手のペースに寄り添うことが信頼につながります。
4-3. ステップ③ 成長やキャリアのテーマへ広げる
1on1の後半では、部下の中長期的な成長やキャリアについて話を広げていきます。
「このままでいいのか?」と漠然と悩む若手や、「本当はリーダーに挑戦したい」と考える中堅社員など、成長の欲求は多様です。
以下のような質問が、対話を広げるヒントになります:
- 「今、何に一番やりがいを感じてる?」
- 「1年後にどうなっていたら嬉しい?」
- 「他部署で気になる仕事、ある?」
この対話の目的は、“答え”を出すことではなく、部下自身に考えてもらうことです。
「考える場がある」という体験自体が、成長のきっかけになります。
4-4. ステップ④ 次回につながる「振り返りと約束」
最後は、その日話したことを一緒に軽く振り返り、次回への布石を打ちます。
- 「今日はこんな話ができてよかったね」
- 「じゃあ、次は○○について話してみようか」
- 「この話、次も少し続けてみようか」
あくまで軽やかに、ポジティブに終えることが大切です。
1on1は「完結」させる場ではなく、「対話を積み重ねていく場」です。
次回も「話したい」と思ってもらえるような余韻を残すことが、継続的な信頼関係を築く鍵になります。
5. 1on1ミーティングの本質的な効果とは?

5-1. 表面的ではない“信頼関係”を築く
信頼関係というと、日々のやりとりや一緒に働く中で自然と築かれるものだと思われがちです。
しかし、深い信頼は、偶発的には生まれません。
特にマネージャーと部下の関係においては、「意識的な対話の機会」が不可欠です。
1on1ミーティングは、
- 上司が部下に“目を向ける”ための時間
- 部下が“安心して心を開ける”ための時間
このふたつが重なって、初めて信頼が育まれます。
そしてこの信頼が、
- 本音の共有
- 早期の問題発見
- 心理的安全性の向上
に直結していくのです。
5-2. 部下の成長を“促進”するスイッチになる
人は「考える場」「認められる場」があって初めて、自ら成長しようという意欲が湧いてきます。
1on1は、部下の思考を促し、言語化を促し、そしてフィードバックを与える――成長のスイッチを入れる場です。
とくに、以下のような変化を生み出しやすくなります:
- 自己認識の向上:「自分の強み・課題は何か?」が見えてくる
- モチベーションの内発化:「なぜこの仕事をしているのか?」を問い直せる
- 挑戦への後押し:「やってみよう」という気持ちに火がつく
このような“内省と挑戦のサイクル”は、日常の中ではなかなか得がたいものです。
だからこそ、定期的な1on1が、個の成長エンジンとして機能します。
5-3. 組織の“対話文化”をつくる
1on1は「一対一の会話」ですが、その影響は個人にとどまりません。
むしろ、本質的な効果は組織文化への波及にあります。
継続的に質の高い1on1が行われている組織では、
- 他のミーティングでも傾聴や共感が自然に行われる
- 部下同士のフィードバックが活性化する
- マネージャーのコミュニケーション全体が丁寧になる
など、“対話を通じて育てる文化”が根づいていきます。
この文化が根づけば、組織は変化への適応力や内発的な動機づけを備える、しなやかで強い集団へと進化していきます。
5-4. 離職防止・エンゲージメント向上にも直結する
「退職理由の本音は、上司との関係性だった」――
こうした調査結果は、国内外問わず多く存在します。
米国Gallup社の調査では、「従業員のエンゲージメントの70%以上がマネージャーによって左右されると報告されています。」というデータもあります。
【引用:Gallup「STATE OF THEAMERICANMANAGER」】
つまり、1on1は離職防止策であり、エンゲージメント向上施策でもあるのです。
日々の対話の中で、
- 「この人は自分に関心を持ってくれている」
- 「話を聞いてくれる」
- 「必要なときに支えてくれる」
と部下が感じることが、定着や満足感に強く影響するのは想像に難くありません。
6.aundのファシリテーターがサポートする1on1の可能性
6-1. 1on1が「うまくいかない現場」には、共通の悩みがある
1on1ミーティングの導入は、多くの企業で進んでいます。
しかしその現場では、以下のような悩みが繰り返し聞こえてきます。
- 「1on1が雑談で終わってしまう」
- 「部下が話してくれない」
- 「やっているけれど成果が感じられない」
- 「結局、評価の話ばかりになってしまう」
これは、マネージャーに熱意や誠実さがないわけではありません。
むしろ、どう進めてよいかの“型”や“対話力”が整っていないことが多いのです。
6-2. 第三者が“鏡”になる。ファシリテーターの価値とは
aundでは、こうした悩みを解決するために、外部の専門ファシリテーターが1on1の場や準備プロセスをサポートします。
その役割は、単なる進行支援ではありません。
ファシリテーターは、
- 対話の質を高める「問い」や「傾聴」の技術をその場で可視化
- マネージャーと部下双方にフィードバックを提供
- 安心安全な場づくりを支援し、本音が出る土壌をつくる
- ミーティング後の振り返りによって“自走できる力”を育てる
つまり、ファシリテーターは“1on1の型”と“信頼関係構築のスキル”を組織に移植する媒介者なのです。
6-3. aundの1on1支援プログラムの特長
aundが提供する1on1支援プログラムは、以下のような構成で実施されます:
| 内容 | 概要 |
|---|---|
| 初期セッション | 管理職向けの1on1設計ワークショップ(目的・構造・進め方) |
| 実践フェーズ | ファシリテーターによる1on1同席(またはレビュー)×数回 |
| フォローアップ | 実施状況の可視化、マネージャーとの振り返りコーチング |
| 成果測定 | 簡易サーベイでエンゲージメントや関係性の変化を可視化 |
これにより、単なる研修では終わらず、**現場での“再現性”と“定着”**にまでフォーカスします。
6-4. 対話が変われば、組織が変わる
「部下との1on1が楽しみになった」
「評価面談では聞けない“本音”が引き出せた」
「会話が変わるとチームの雰囲気まで変わる」
――これは、実際にaundのサポートを受けた現場の声です。
1on1ミーティングは、あくまで“きっかけ”です。
本当に変えるべきは、その背後にある関係性の質であり、対話の文化です。
ファシリテーターという第三者の存在が、それを動かすカギになるのです。
6-5. ご相談・お問い合わせはこちらから
1on1を“施策”で終わらせたくない方へ。
aundは、対話のプロフェッショナルとして貴社に寄り添います。
詳しくは、サービス紹介ページをご覧ください。
まずは気軽に相談(無料)を活用ください。


