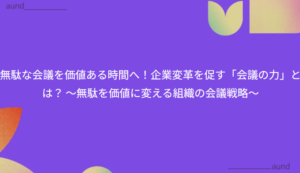「7S × バリューチェーン」から学ぶ企業成長の原則:組織の強化と競争優位を生む構造戦略

「7S × バリューチェーン」から学ぶ企業成長の原則
~組織の強化と競争優位を生む構造戦略~
目次
1. 序論:企業成長には「7S」と「バリューチェーン」の理解が不可欠
〇成功企業はどのように7Sとバリューチェーンを活用しているのか?
〇企業の成長と組織の構造理解がなぜ重要なのか?
〇7Sとバリューチェーンが経営戦略に与える影響
〇組織構造を理解することで経営のボトルネックを解消
2. マッキンゼーの7Sモデルを活用した組織強化
〇7Sによる組織課題の特定と解決策
〇7Sの解説
〇7Sの視点で企業成長を分析する
〇成功企業の7S活用例:P&Gの成長と変革
3. バリューチェーン分析を活用した企業成長戦略
〇企業の利益構造とバリューチェーンの関係性
〇バリューチェーンとは? 企業価値を最大化するフレームワーク
〇バリューチェーンの「主活動」と「支援活動」の整理
〇競争優位性を生むバリューチェーンの最適化
4. 7Sとバリューチェーンの統合で企業成長を加速する
〇意思決定のスピードを向上させる組織マネジメント
〇7Sとバリューチェーンを組み合わせた経営戦略
〇「成長する企業」と「停滞する企業」の組織設計の違い
〇組織の柔軟性を高めるフレームワーク活用
5. 企業が実践すべき組織強化のステップ
〇企業が取り組むべきアクション(組織改革・意思決定プロセスの最適化)
〇aundが提供する組織強化支援サービス
序論:企業成長には「7S」と「バリューチェーン」の理解が不可欠
1-1. 企業の成長と組織の構造理解がなぜ重要なのか?
企業が成長するためには、革新的な製品やサービスの提供だけでなく、組織の内部構造と価値創造のプロセスを最適化することが不可欠です。
しかし、多くの企業は成長の過程で「組織の停滞」に陥ります。その主な原因として、以下のような問題が挙げられます。
- 組織の複雑化による意思決定の遅延
- 縦割り組織(サイロ化)による部署間の連携不足
- 市場環境の変化に適応できない硬直化したビジネスモデル
特に、日本企業では「ピラミッド型組織」が一般的であり、トップダウンの強い指示系統が意思決定のスピードを鈍らせる要因となることが少なくありません。
こうした課題を乗り越え、持続的な競争力を高めるために役立つのが、「マッキンゼーの7Sフレームワーク」と「バリューチェーン分析」です。
ただし、これらのフレームワークは適用するだけで企業が自動的に最適化されるわけではありません。
あくまで、組織の現状を分析し、メンバー間の共通理解を生むための道具であり、それをどのように運用し、改善を進めていくかが成功の鍵となります。

1-2. 7Sとバリューチェーンが経営戦略に与える影響
① 7Sモデルが組織のバランスを整える
マッキンゼーの7Sフレームワークは、組織を構成する重要な要素を整理し、相互のバランスを考えるフレームワークです。
7つの要素は、「ハードの要素」と「ソフトの要素」に分かれます。
- ハードの要素(組織の基盤):戦略(Strategy)、組織構造(Structure)、システム(Systems)
- ソフトの要素(組織の文化や行動):共有価値観(Shared Values)、スタイル(Style)、人材(Staff)、スキル(Skills)

企業が成長する過程で、ハードの要素だけを整えても組織は機能しません。
たとえば、「戦略」と「組織構造」が優れていても、「共有価値観」が浸透していなければ、メンバーが主体的に動かず、組織は硬直化してしまいます。
会社がどこを目指しているのかわからない。と思っている若手メンバーは案外多いのです。
このように、7Sは組織の全体像を理解し、バランスを取るために活用されます。
② バリューチェーン分析が競争優位性を生む
バリューチェーンは、企業がどのように価値を生み出し、競争力を強化するのかを分析するためのフレームワークです。
バリューチェーンは、以下の2つの活動に分かれます。
- 主活動(製品・サービスを生み出す活動)
- 調達、製造、出荷、マーケティング、販売、アフターサービス
- 支援活動(主活動を支える間接的な活動)
- 経営管理、人事、技術開発、調達活動

例えば、ユニクロはバリューチェーン全体を最適化することで、高品質×低価格を両立させたビジネスモデルを実現しました。
【引用:ユニクロ公式サイト「ユニクロのバリューチェーン戦略」https://www.fastretailing.com/jp/group/strategy/uniqlobusiness.html】
自分たちが何からお金を得て、何からサービスを生み出しているかを多角的に分析することが可能なフレームワークです。
このように、バリューチェーンを活用することで、企業がどの領域で競争優位を築くべきかが明確になります。
1-3. 組織構造を理解することで経営のボトルネックを解消
企業の成長が鈍化する主な要因の一つに、組織構造の問題が適切に認識されず、適切な対策が講じられていないことが挙げられます。
特に、組織が拡大するにつれて以下のような経営上のボトルネックが発生しやすくなります。
① 経営層の意思決定が遅れる
企業が成長すると、組織内の情報の流れが複雑になり、経営層が迅速に意思決定を下せなくなることがあります。
特に、トップダウン型の階層的な組織では、意思決定プロセスが長くなり、機会損失を招くことがあります。
例えば、トヨタ自動車はこの課題を克服するために、「現場主導の改善文化」を強化しました。トヨタは「トヨタ生産方式(TPS)」を採用し、従業員一人ひとりが現場で課題を発見し、すぐに対応できる仕組みを構築しました。
この「ボトムアップ型の意思決定」により、組織の階層を超えた柔軟な対応が可能になっていきました。
【引用:戦闘力ビジネス「トヨタの7Sマネジメント戦略」https://business.sentouryoku.com/seven_s/】
どんな会社でも適切な処置を行わないと、組織は官僚的になっていきがちです。
それを未然に防ぐための対策が必要となります。
② 部門間のサイロ化(縦割り)が進む
企業が成長し、部署が増えるにつれて、それぞれの部署が独自の目標や評価基準を持ち始めることがあります。
その結果、部門間のコミュニケーションが希薄になり、企業全体のパフォーマンスが低下することがあります。
例えば、ユニクロでは、バリューチェーンを活用して部門間の壁を取り払い、調達から販売までのプロセスを統合管理する戦略を採用しました。
この結果、情報共有の円滑化と業務の効率化を実現し、迅速な市場対応が可能になりました。
【引用:ユニクロ公式サイト「ユニクロのバリューチェーン戦略」https://www.fastretailing.com/jp/group/strategy/uniqlobusiness.html】
各部署が自律的に動いていくのは非常に意味があります。
しかし、全体最適な視点をおろそかにすると、全体の利益が損なわれることも忘れてはいけません。
③ 経営層と現場の認識ギャップが生まれる
企業が成長するにつれ、経営層と現場の間に認識のズレが生じることがあります。
経営層が掲げる戦略が現場で実行されにくくなり、組織全体の一体感が失われることがあります。
P&Gでは、この問題を解決するために、7Sの「共有価値観(Shared Values)」を組織の基盤とし、社員全員が共通の目標を持つ文化を構築しました。
これにより、組織の一体感を強化し、各レベルの社員が自律的に行動できるようになりました。
【引用:S.C. Digital「P&Gの組織文化と7Sの関係性」https://www.scdigital.co.jp/knowledge/2426/】
経営と現場ではどうしても距離がでてしまうものです。
それを防いでいくための施策や、経営にも近づいていこうとするマインドセットも求められるでしょう。
このように、7Sモデルやバリューチェーンを適切に活用することで、企業の組織課題を可視化し、適切な改善策を講じることが可能です。
1-4. 成功企業はどのように7Sとバリューチェーンを活用しているのか?
成功企業は、7Sとバリューチェーンを単なる理論ではなく、実際の経営戦略に組み込むことで競争力を強化しています。
ここでは、具体的な企業事例をもとに、それらがどのように活用されているかを解説します。
① Amazon:バリューチェーンの最適化による競争優位
Amazonは、バリューチェーンの最適化を徹底し、物流、倉庫管理、データ分析を高度に統合することで、市場支配力を維持しています。
特に、AIを活用したリアルタイムの需要予測と、高度に自動化された物流システムが、競争力の源泉となっています。
例えば、Amazonの物流センターでは、ロボティクス技術とAIを活用し、在庫管理と配送のスピードを最大化しています。
この仕組みにより、配送コストを削減しつつ、顧客満足度の向上を実現しています。
【引用:Business Model Analyst「Amazonのバリューチェーン戦略」https://businessmodelanalyst.com/amazon-value-chain-analysis/?srsltid=AfmBOoosDH85JF8GQ_nuGiz91ME6aGzSiFAnXDQDJ3oS5xZX_cV_BCPR】

② トヨタ:7Sを活用した組織マネジメント
トヨタは、7Sの「システム(Systems)」と「スキル(Skills)」を活用し、現場の自律性を高めることで組織の競争力を向上させています。
特に「トヨタ生産方式(TPS)」は、7Sの原則に基づいたものであり、社員一人ひとりが継続的に業務改善を行う文化が確立されています。
例えば、以下のような取り組みが実践されています。
- 「かんばん方式」によるジャストインタイム生産
- 「現場主導の改善文化」(カイゼン活動)の徹底
- 「組織の知識継承」(OJTを通じたスキルの共有)
これらの仕組みは、トヨタが競争環境の変化に迅速に対応するための強固な基盤となっています。
【引用:戦闘力ビジネス「トヨタの7Sマネジメント戦略」https://business.sentouryoku.com/seven_s/】

③ P&G:7Sの「共有価値観」を活かした経営
P&Gは、7Sの「共有価値観(Shared Values)」と「スタイル(Style)」を重視することで、社員の主体性と創造性を高めています。
特に、「Purpose-Driven (目的駆動)」の実践により、社員全員が会社のビジョンに沿って行動する文化を確立しました。
例えば、P&Gは以下のような仕組みを導入しています。
- 全社共通の企業理念を浸透させる「P&G Culture」
- リーダーシップ研修の徹底
- データを活用した戦略的意思決定の強化
このように、P&Gは7Sを活用して、組織文化の維持と競争力の強化を両立させています。
【引用:Forbus「P&G は目的主導のストーリーテリングで企業基準を設定」https://www.forbes.com/sites/brandstorytelling/2021/11/16/pg-sets-the-corporate-standard-with-purpose-driven-storytelling/】

マッキンゼーの7Sモデルを活用した組織強化
2-1. 7Sによる組織課題の特定と解決策
7Sモデルは「企業の変革に必要な視点」を整理する道具
企業は成長の過程で多くの組織課題に直面しますが、問題の本質がどこにあるのかを適切に見極められないまま施策を打つケースは少なくありません。例えば、売上低迷の原因が「戦略の欠陥」にあるのか、それとも「組織の実行力」にあるのかを見誤ると、的外れな改革を行ってしまい、かえって混乱を招きます。
マッキンゼーの7Sモデルは、このような「問題の本質を可視化する」ためのツールとして活用できます。
特に、企業が成長する過程では、7Sのバランスが崩れやすく、何か1つの要素だけを改革しても全体として機能しないことがあります。例えば、組織をフラット化しようとしても、評価システム(Systems)が旧来の階層型のままだと、従業員の行動様式は変わりません。
そんな時は、7S全体を俯瞰的にとらえる事が重要です。
部分でとらえず、全体を捉える意識が必要です。
7Sを用いることで、組織改革を進める際に「何をどう変えればよいのか」を整理し、効果的な施策を設計することが可能になるのです。
2-2. 7Sの解説——ハード要素とソフト要素の相互作用
7Sは 「ハードな要素(管理・構造)」 と 「ソフトな要素(文化・人材)」 の2つに分かれます。これらは単独で機能するものではなく、相互に影響し合いながら組織全体の成長に貢献します。
| 分類 | 要素 | 概要 |
|---|---|---|
| ハード要素 | 戦略(Strategy) | 企業の競争優位性をどのように築くか |
組織構造(Structure) | 役割分担、階層構造、権限の分布 | |
| システム(Systems) | 業務プロセス、評価・管理の仕組み | |
| ソフト要素 | 共有価値観(Shared Values) | 企業文化、ミッション、経営理念 |
| スタイル(Style) | 経営スタイル、リーダーシップの特徴 | |
| 人材(Staff) | 人材の採用、配置、育成の方針 | |
| スキル(Skills) | 組織全体の専門性や技術的強み |
企業は、「ハード面を整備すれば組織が機能する」と考えがちですが、実際には「ソフト要素」がハード要素の効果を左右する ことが多々あります。
例えば、急速に拡大した企業が組織構造(Structure)を整えても、企業文化(Shared Values)が旧来のままだと、新しい組織体制が機能せず、従業員の行動が変わらないという事態が発生します。このように、組織の改革にはハード要素とソフト要素を統合的に見直すことが不可欠です。
2-3. 7Sの視点で企業成長を分析する——企業の成長フェーズごとの課題
企業は成長の各フェーズで異なる課題に直面します。7Sを用いることで、それぞれの段階で何を強化すべきかが明確になります。下記は一例ですが、自社がどのフェーズにおり、何をするかの参考にはなるかと思います。
| 成長フェーズ | 重点7S要素 | 典型的な課題 |
|---|---|---|
| 創業期 | ストラテジ(戦略)、スキル | 事業戦略の明確化、専門スキルの不足 |
| 成長期 | 組織構造(Structure)、人材(Staff) | 人員増加に伴う組織の矛盾、リーダー層の育成 |
| 安定期 | 共有価値観(Shared Values)、システム(Systems) | 文化の形骸化、業務プロセスのハード直化 |
| 変革期 | ストラテ時(戦略)、スタイル | 競争環境への適応、リーダーシップの再構築 |
例:創業期の企業はスキル(Skills)が不足しているため、優秀な人材の確保が急務です。
企業が変革を成功させるには、成長段階ごとに正しいな7Sの要素に注力することが必要になってくるといえるでしょう。
2-4. 成功した企業の7S活用事例:P&Gの成長と変革
P&G(プロクター・アンド・ギャンブル)は、1837年に米国で創業し、消費財業界を牽引してきたグローバル企業です。200年以上の歴史の中で、市場環境の変化に適応しながら組織を変革してきました。その成功の背景には、マッキンゼーの7Sモデルの要素を活用し、企業の基盤を整えてきたことが挙げられます。本章では、7Sモデルの視点からP&Gの組織変革の軌跡を分析し、成長を続けるための戦略を読み解きます。
① Strategy(戦略):オープンイノベーションと事業ポートフォリオの最適化
P&Gは、2000年代初頭に「Connect + Develop(C+D)」というオープンイノベーション戦略を導入しました。これは、社外の技術やアイデアを積極的に取り入れ、新商品開発のスピードと成功率を向上させるための戦略です。
- 2000年代以前、P&Gは製品開発を社内リソースに依存していました。しかし、競争環境の変化と技術革新の加速により、外部の技術やスタートアップとの連携が不可欠となりました。
- C+D戦略の導入後、P&Gは「パンパース」「スワイファー」などのヒット商品を市場に投入し、製品開発の効率化に成功しました。
また、P&Gは過去20年間で事業ポートフォリオを大幅に見直し、不採算事業を売却することで収益性を高めました。たとえば、美容ブランドの一部を売却し、コア事業である消費財に経営資源を集中させています。
② Structure(組織構造):シンプルで機動的な組織への移行
かつてのP&Gは、多層的な組織構造を持ち、意思決定のスピードが遅いという課題を抱えていました。しかし、2014年以降、組織のスリム化を進め、より機動的な組織への転換を図りました。
- 地域・製品ごとに細分化されていた組織を統合し、意思決定を迅速化。
- 階層を減らし、部門間の連携を強化する体制へ移行。
- デジタルツールを活用し、経営判断のスピードを向上。
この組織変革により、グローバル規模での業務効率が向上し、市場変化への対応力が強化されました。
③ Systems(システム):デジタル変革とAI活用
P&Gは、デジタル技術を活用し、業務の最適化を推進しています。
- 「P&G Ventures」を立ち上げ、デジタル技術を活用した新事業の創出を支援。
- AIを活用した消費者データ分析を強化し、市場のニーズに即した商品開発を実現。
また、サプライチェーンの最適化にも力を入れ、生産・物流・販売の全工程をデジタルで可視化する取り組みを進めています。
④ Shared Values(共有価値観):企業理念の浸透とESG経営の推進
P&Gは「Purpose, Values, and Principles(PVP)」という企業理念を掲げ、これを全社員が共有しています。【引用:P&G公式】
- 「消費者を中心に考える」という価値観を重視し、全ての意思決定の基準に設定。
- ESG経営を推進し、サステナブルな商品開発と社会貢献活動を強化。
企業理念の徹底により、グローバル企業としての社会的責任を果たしつつ、企業価値を向上させています。
⑤ Style(経営スタイル):リーダーシップと組織文化
P&Gの経営スタイルの特徴は、「成長を促すリーダーシップ」の推進です。
- CEO主導のトップダウン型ではなく、現場の判断力を尊重する経営スタイルを採用。
- 社内教育プログラムを充実させ、社員のリーダーシップ育成を強化。
これにより、組織全体のアジリティ(機動力)が向上し、変化に柔軟に対応できる企業文化が醸成されています。
⑥ Staff(人材):ダイバーシティとグローバル人材戦略
P&Gは、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を経営戦略の柱としています。
- 管理職の**女性比率を50%**に引き上げ、多様なリーダー育成を推進。
- グローバルな人材配置を行い、各地域の市場に適応した経営を実施。
これにより、市場ごとのニーズに対応しやすい体制を確立しています。
⑦ Skills(スキル):デジタルスキルと専門能力の向上
P&Gは、社員のスキルアップを支援するため、デジタル技術やデータ分析スキルの研修プログラムを提供しています。
- AI活用スキルのトレーニングを実施し、従業員のデジタルリテラシーを向上。
- 社内ラーニングプラットフォームを活用し、継続的なスキル開発を促進。
これにより、イノベーション創出の土台を強化しています。【引用:P&G公式】
3.バリューチェーン分析を活用した企業成長戦略
企業が成長し続けるためには、自社の利益構造を正しく理解し、競争力を強化する戦略を練ることが不可欠です。そのための強力なフレームワークとしてバリューチェーン分析が挙げられます。バリューチェーン(価値連鎖)を分析することで、企業がどのプロセスで価値を生み出しているのか、あるいは競争優位を確立するためにどの部分を最適化すべきかを明確にすることができます。
本章では、バリューチェーンが企業成長にどのように貢献するのかを整理し、その実践的な活用方法を探ります。
3-1. 企業の利益構造とバリューチェーンの関係性
企業の利益は、単純に製品やサービスを売ることによって生まれるわけではありません。その裏には、調達から製造、販売、マーケティング、アフターサービスに至るまで、多くの要素が関与しています。この一連のプロセスの中で、価値を生み出す部分とコストを発生させる部分を正しく理解することが、企業の利益構造を最適化する鍵となります。
バリューチェーン分析を活用すると、企業の事業活動を「価値を生むプロセス」と「コストを生むプロセス」に分類し、それぞれの役割や影響度を明確にできます。例えば、製造業であれば調達コストの削減が重要かもしれませんし、IT企業であれば開発スピードやUX向上が競争優位性に直結するでしょう。つまり、企業の利益を最大化するためには、自社のビジネスモデルを分解し、どのプロセスが「強み」なのか、どの部分を「改善」すべきかを理解する必要があります。

3-2. バリューチェーンとは? 企業価値を最大化するフレームワーク
バリューチェーンとは、企業が製品やサービスを市場に提供するために行う一連の活動を分析するフレームワークです。この概念は、マイケル・ポーターが提唱したものであり、企業の競争優位性を理解し、戦略的な意思決定を行うために広く活用されています。
バリューチェーンのポイントは、「企業の活動を個別に分解し、それぞれの価値とコストを明確にすること」です。これにより、競争力を高めるために強化すべきプロセスや、効率化によってコスト削減が可能な部分を特定できます。
例えば、バリューチェーンを活用することで、次のような疑問に答えることができます:
- 自社の強みはどこにあるのか?
- 競争他社と比較して優位に立てる領域はどこか?
- コストを削減する余地はあるか?
- 顧客への価値提供を最大化するためには何を強化すべきか?
これらの問いに答えることで、企業は自社の持続的成長を支える戦略を具体的に設計できるのです。
3-3. バリューチェーンの「主活動」と「支援活動」の整理
バリューチェーンは、企業の事業活動を「主活動(Primary Activities)」と「支援活動(Support Activities)」の2つに分けて整理します。
① 主活動(Primary Activities)
主活動とは、製品やサービスを市場に届けるまでの直接的なプロセスのことを指します。以下の5つの要素が含まれます:
- 調達(Inbound Logistics)
- 原材料や部品の調達・保管・在庫管理
- サプライヤーとの関係性構築が重要
- 製造(Operations)
- 生産プロセスの最適化と効率化
- 省人化・自動化による生産性向上
- 出荷物流(Outbound Logistics)
- 製品の保管・配送・在庫管理
- 物流ネットワークの最適化
- マーケティングと販売(Marketing & Sales)
- ブランド戦略、広告、プロモーション活動
- 営業戦略と顧客獲得のプロセス
- アフターサービス(Service)
- 顧客サポート、保証、メンテナンス
- 継続的な顧客関係の構築
② 支援活動(Support Activities)
支援活動は、主活動を円滑に進めるための間接的なプロセスです。以下の4つの要素があります:
- 全般管理(Firm Infrastructure)
- 経営戦略、組織運営、財務・法務管理
- 人事管理(Human Resource Management)
- 人材採用、研修、育成、組織文化の形成
- 技術開発(Technology Development)
- 研究開発、デジタル技術の活用、プロセス革新
- 調達(Procurement)
- 仕入れ戦略、コスト削減、サプライヤー管理
このように、企業の活動を分解することで、どのプロセスが価値を生み出し、どこにコスト削減の余地があるのかを明確にすることができます。
3-4. 競争優位性を生むバリューチェーンの最適化
バリューチェーンの最適化とは、競争力を高めるために各活動の強化や効率化を図ることを指します。最適化のアプローチには大きく2つの方向性があります。
① コストリーダーシップ戦略
コストリーダーシップ戦略とは、コストを徹底的に削減し、競争力のある価格設定を可能にするアプローチです。
- 調達コストの削減
- サプライチェーンの合理化や大量発注によるコストカット
- 製造の効率化
- 自動化技術の導入による人件費の削減
- 物流の最適化
- 在庫管理の効率化と配送ルートの最適化
② 差別化戦略
差別化戦略とは、独自性のある価値を提供し、競争優位性を確立するアプローチです。
- ブランド価値の向上
- デザインや品質で他社と差別化
- 顧客体験の強化
- アフターサービスの充実やCX(カスタマーエクスペリエンス)の向上
- 技術革新の推進
- 研究開発に投資し、新技術を活用した新商品の開発
バリューチェーンを最適化することで、企業はコスト競争力を高めながら独自性を確立し、持続的な成長を実現できるのです。
バリューチェーン分析は、企業の利益構造を理解し、競争力を高めるための強力なフレームワークです。企業活動を「主活動」と「支援活動」に分け、それぞれの最適化を図ることで、持続的な成長が可能になります。
4. 7Sとバリューチェーンの統合で企業成長を加速する
7Sフレームワークとバリューチェーンは、それぞれ異なる視点から企業の成長を分析するためのツールですが、これらを統合的に活用することで、より強固な経営基盤を築くことが可能になります。7Sは「組織の構造や文化」、バリューチェーンは「企業活動の価値創造の流れ」に焦点を当てるため、両者を掛け合わせることで、企業の強みを活かしつつ、課題の本質をより明確にできるのです。
本章では、7Sとバリューチェーンを組み合わせた企業成長戦略について掘り下げ、組織の柔軟性を高める方法を探っていきます。
4-1. 意思決定のスピードを向上させる組織マネジメント
なぜ意思決定のスピードが企業成長に影響を与えるのか?
市場の変化が激しい現代において、意思決定の遅れは企業にとって致命的なリスクとなります。特に、日本企業に多く見られる「階層型のピラミッド組織」では、承認プロセスが多く、経営層の判断が現場に浸透するまでに時間がかかることが課題です。一方で、スタートアップや成長企業では、フラットな組織構造を採用し、現場の裁量権を高めることで、迅速な意思決定を可能にしています。
意思決定のスピードを上げるための組織マネジメントのポイント
Amazonではバリューチェーンの各プロセスにKPIを設け、リアルタイムのデータを基に意思決定を行っています。
組織の透明性を高める
7Sの「共有価値(Shared Values)」を明確にし、組織全体で一貫した意思決定ができる環境を構築しています。
例えば、Googleではミッションとバリューを全社員が共有し、それに沿った意思決定が迅速に行われています。
現場への権限移譲(デリゲーション)を進める
トップダウン型の組織から、各チームに裁量権を持たせるマトリクス型組織へと移行させることもひとつの手です。
バリューチェーンの「主活動」と「支援活動」ごとに権限を適切に分散し、迅速な判断を可能にしていきます。
データドリブンな意思決定の導入
勘や経験に頼るのではなく、データ分析を活用して迅速な判断ができる環境を整備することも心掛けましょう。
4-2. 7Sとバリューチェーンを組み合わせた経営戦略
7Sとバリューチェーンは、互いに補完し合うフレームワークとして機能します。7Sは組織文化や内部の仕組みにフォーカスし、バリューチェーンは企業活動そのものに着目するため、両者を組み合わせることでより包括的な経営戦略を立案できます。

統合的な視点での経営戦略のポイント
戦略(Strategy) × バリューチェーンの最適化
企業が持つ競争優位性を明確にし、それに基づいたバリューチェーンの設計を行っていきましょう。
例:ユニクロは「ファストファッション」の戦略を掲げ、調達から販売までのバリューチェーンを最適化することで、業界内での優位性を確立しています。【引用:ユニクロのビジネスモデル】
組織構造(Structure) × 価値創造プロセスの整理
ピラミッド型組織とフラット型組織のどちらが適しているかを業態に応じて判断し、組織の形を最適化することも考えましょう。
例:P&Gは、各ブランドを独立したビジネスユニットとして機能させ、迅速な意思決定を可能にしています。
共有価値観(Shared Values) × ブランド戦略
企業文化を徹底し、ブランドと一致した価値を社内外で共有することも重要です。
例:Appleは「デザインと使いやすさ」という企業理念をバリューチェーン全体に落とし込み、競争優位性を確立しています。
4-3. 「成長する企業」と「停滞する企業」の組織設計の違い
成長する企業と停滞する企業では、組織設計とバリューチェーンの活用の仕方が根本的に異なります。
成長企業の特徴
- 意思決定が迅速で、情報がスムーズに流れる
- 市場変化に柔軟に対応できる
- バリューチェーンの各プロセスで競争優位性を確立している
- 7Sを活用し、組織文化を明確にしている
停滞企業の特徴
- 7Sの要素がバラバラで、企業全体の方向性が統一されていない
- 意思決定のプロセスが複雑で遅い
- 変化に対して抵抗が強い
- コスト削減にのみフォーカスし、価値提供の向上を軽視
4-4. 組織の柔軟性を高めるフレームワーク活用
企業が市場の変化に適応し、持続的な成長を遂げるためには、組織の柔軟性を高めることが不可欠です。組織の柔軟性とは、単に「フラットな組織にする」ことではなく、環境の変化に応じて適切な意思決定が迅速に行える仕組みを整備することを指します。
7Sモデルとバリューチェーンを活用しながら、どのように組織の適応力を高めることができるのかを詳しく見ていきましょう。
1. 変化する市場環境に適応するためのバリューチェーンの最適化
市場環境が変化する中で、企業が競争力を維持・向上させるためには、バリューチェーンを静的なものとして捉えるのではなく、常に動的に見直しを行うことが重要です。たとえば、デジタル技術の発展により、企業の販売チャネルや物流システムは急速に変化しています。
事例:Amazonのバリューチェーンの進化
Amazonは創業当初、書籍販売に特化し、物流を外部委託していました。しかし、事業の拡大とともに、物流ネットワークを自社で構築し、ラストワンマイルの配送を強化することで、競争優位性を確立しました。この変化は、単なる業務効率化ではなく、企業の提供価値を大幅に向上させるものでした。【引用:Amazonのバリューチェーン分析】
ポイント
- デジタル技術を活用して、業務効率と顧客体験を同時に向上させる
- 市場環境が変化するたびに、バリューチェーンの見直しを行うことが重要
- 外部委託すべきプロセスと、内製化すべきプロセスを適切に判断する
2. 7Sの要素を組み替えながら変革を進める
7Sフレームワークは、組織の成長ステージに応じて最適な形に組み替えることができます。たとえば、スタートアップ企業では、「戦略(Strategy)」と「スキル(Skills)」に重点を置き、革新性を強化する一方で、成熟企業では「構造(Structure)」と「システム(Systems)」の最適化が重要になります。
事例:トヨタの7S活用と組織変革
トヨタは、長年にわたり「TPS(トヨタ生産方式)」を支える組織文化を維持しつつ、市場環境の変化に適応するために7Sの「共有価値(Shared Values)」と「スキル(Skills)」を強化してきました。
特に、カイゼン文化の浸透は、トヨタの7S活用の典型例です。社員一人ひとりが改善の視点を持ち、組織全体が変化に適応する柔軟な仕組みを確立しています。【引用:トヨタの7S活用】
ポイント
- 変革を組織全体に根付かせるための文化醸成が鍵となる
- 組織の成長フェーズに応じて、7Sの要素を重点的に組み替える
- 市場の変化に応じて「共有価値」や「スキル」を進化させる
3.企業の柔軟性を高めるための具体的なアプローチ
① 経営陣と現場のコミュニケーションを強化
- フレームワークを活用して、経営層と現場の認識を揃える
- 7Sの「共有価値」を定期的に見直し、組織全体の方向性を統一
② データドリブンな意思決定
- バリューチェーンの各プロセスでデータを活用し、最適な意思決定を行う
- AIやBIツールを導入し、リアルタイムでの経営判断を実現
③ 定期的な組織アセスメント
- バリューチェーンの各プロセスを定期的に分析し、競争優位性を維持
- 7Sを活用し、組織の強みと課題を定期的に評価
組織の柔軟性を高めるには、7Sとバリューチェーンを連携させ、企業の成長フェーズに応じて最適な形に組み替えることが重要です。市場環境が変化する中で、企業が持続的に成長し続けるためには、経営戦略・組織設計・価値創造プロセスを統合的に捉え、変化に対応できる体制を整えることが不可欠です。
5. 企業が実践すべき組織強化のステップ
企業の持続的成長には、適切な組織強化の取り組みが不可欠です。「7S」と「バリューチェーン」を活用し、組織の構造と運営を最適化することで、意思決定のスピードを高め、競争優位性を確立することができます。
本章では、企業が実践すべき組織強化の具体的なステップと、それを支援する aund のサービス について紹介します。
5-1. 企業が取り組むべきアクション(組織改革・意思決定プロセスの最適化)
1. 組織改革の方向性を明確にする
組織改革の第一歩は、企業がどのような目的で変革を進めるのかを明確にすることです。
例えば、次のような目的が考えられます。
- 市場環境の変化に対応し、競争力を強化する
- 迅速な意思決定ができる組織を構築する
- 社員のエンゲージメントを高め、組織の一体感を強化する
- 業務効率化を推進し、不要なコストを削減する
企業の成長ステージによっても最適な組織構造は異なります。7Sを活用して自社の組織を分析し、強化すべき要素を特定することが重要です。
2. 意思決定プロセスの最適化
組織改革において、「意思決定のスピードと質」 は非常に重要な要素です。
企業が迅速な意思決定を実現するためには、次のような施策を取り入れることが有効です。
① 意思決定の分散化
従来のピラミッド型組織では、すべての決定が上層部に集中しがちです。その結果、意思決定に時間がかかり、現場の柔軟性が失われることになります。
これを解決するために、「アジャイル型の組織運営」を取り入れ、現場に裁量を持たせることで迅速な対応を可能にします。
② データドリブンな経営
意思決定を感覚ではなく、データに基づいて行うことも重要です。
バリューチェーンの各プロセスでデータを活用し、現状を可視化することで、経営判断の精度を向上させることができます。
③ 会議体の最適化
会議の運営が非効率だと、意思決定のスピードが落ちてしまいます。
「会議の目的を明確にし、短時間で結論を出す仕組み」を整えることで、会議の生産性を向上させることが可能です。
5-2. aundが提供する組織強化支援サービス
aund は、企業の組織強化と会議の最適化をサポートする専門サービスを提供しています。
「組織の構造を見直し、意思決定をスムーズにし、成果を最大化する」ために、次のようなプログラムを展開しています。
1. 会議の型作り研修|効果的な会議運営スキルを習得し、組織の成果を最大化
組織の課題の多くは「会議の運営方法」にあるといわれています。
本研修では、成果を生む会議の運営技術を学び、組織の生産性向上を支援します。
「会議が長引いて結論が出ない」「議論が発散してしまう」といった課題を抱える企業に最適です。
📌 主な内容
- 効果的な会議のフレームワーク
- ファシリテーションスキルの向上
- 意思決定の迅速化
👉 詳細はこちら:会議の型作り研修
2. 会議ファシリテーター養成研修|議論を導くプロフェッショナルになる
管理職やリーダー向けに、会議の進行スキルを強化するための研修です。
会議の質を高めることで、組織全体の意思決定をスムーズにし、戦略実行力を向上させることが目的です。
📌 主な内容
- 会議の設計方法
- ファシリテーションスキルの習得
- 組織の合意形成力の強化
👉 詳細はこちら:会議ファシリテーター養成研修
3. 3か月でチームが進化する|自律型組織を実現するファシリテーター伴走サービス
「会議が変われば、チームが変わる。そして組織が動き出す。」
このプログラムでは、プロのファシリテーターが3か月間伴走し、組織の自律性を高めるサポートを行います。
📌 主な内容
- 会議の設計・進行の支援
- 組織のコミュニケーション改善
- 意思決定プロセスの最適化
👉 詳細はこちら:ファシリテーター伴走サービス
4. 成果の出るチームビルディング支援サービス|信頼と結束力で組織を強化
組織のパフォーマンスを最大化するには、チーム全体の一体感を高めることが不可欠です。
本プログラムでは、チームの信頼関係を構築し、目標達成に向けた強固なチーム作りを支援します。
📌 主な内容
- チームの心理的安全性を高める
- コミュニケーションの改善
- チームパフォーマンスの向上
👉 詳細はこちら:チームビルディング支援