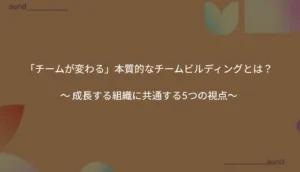会議がうまくいかない本当の理由:成果を左右する“ソフトスキル”とは?

会議がうまくいかない本当の理由
~成果を左右する“ソフトスキル”とは?~
目次
1.はじめに:会議が「機能しない」と感じるのはなぜか?
2.ソフトスキルとは何か?なぜ今、注目されるのか
3.ソフトスキル不足がもたらす“会議の機能不全”
4.会議を機能させるためのソフトスキル5選
5.ソフトスキルは“研修だけ”では育たない
6.aundのアプローチ:ソフトスキルで会議と組織を変える
1.はじめに:会議が「機能しない」と感じるのはなぜか?
「また意味のない会議だったな…」
「結局、何が決まったのかよく分からなかった」
「一部の人だけが話していて、私は何のためにいたんだろう」
これは、決して珍しい感想ではありません。会議というと本来、意思決定や情報共有、アイデアの創出、組織の関係性づくりなど多くの目的があります。しかし現実には、それらが達成されていない「なんとなく集まっただけ」の会議が驚くほど多く存在しています。
このように「会議がうまくいっていない」と感じるとき、私たちはその原因を、アジェンダの不在や会議時間の長さ、司会進行の不慣れといった“ハード面”に求めがちです。確かに、これらも会議の質を左右する重要な要素です。しかし、そうした外面的な「設計」だけを整えても、会議が必ずしも機能するとは限りません。
実際に、ファシリテーションが洗練されたアジェンダ通りに進んでいるにもかかわらず、参加者の間に緊張感が漂い、深い意見が交わされない場を目にしたことはないでしょうか。
なぜそのような“表面的には整っているのに、実質的に空虚な会議”が生まれるのでしょうか?
答えは、ソフトスキルの不足にあります。
会議とは、あくまで「人」と「人」が向き合う場です。どんなに優れた仕組みがあっても、それを動かすのはメンバー一人ひとりの意識と関係性。つまり、傾聴する力、意見を伝える勇気、異なる意見を調整し合う力、対話を通じて合意を形成する力——これらのソフトスキルがなければ、会議の場はただの報告会や独り言の発表になってしまいます。
近年、GoogleやMetaといったグローバル企業が「ソフトスキルこそが組織の競争力」と捉えているのは、まさにこの点に起因します。
これからの記事では、「ソフトスキルとは何か?」を丁寧に解き明かしながら、それが会議の質にどのように影響し、どうすれば育てていけるのかを解説していきます。
【参考記事】:「【必見!】ソフトスキルで実行力を劇的に高める!会議を創造の場に変えるために必要なこととは?」
2.ソフトスキルとは何か?なぜ今、注目されるのか
2-1. ソフトスキルとは?
ソフトスキルとは、一言でいえば「人と関わる力」です。専門知識や技術(ハードスキル)とは異なり、人間関係の構築、コミュニケーション、協働、共感、問題解決、感情のコントロールといった、主に「非認知スキル」に分類される能力を指します。
たとえば会議においては、
- 相手の話を最後まで聴く力(傾聴)
- 自分の意見を論理的かつ柔らかく伝える力
- 対立を前向きに収束させる力(合意形成)
- 沈黙や空気に気づく察知力 などが、ソフトスキルの具体例です。
このようなスキルは、明文化しにくく、テストで数値化されるものでもありません。けれども、組織やチームが「人の集まり」である限り、最も重要な基盤となる力だと言っても過言ではありません。
2-2. なぜ今、ソフトスキルが求められるのか?
近年、ソフトスキルへの注目度が飛躍的に高まっている背景には、いくつかの大きな変化があります。
(1)複雑性の増すビジネス環境
市場の変化が激しく、正解のない課題に向き合う機会が増えるなか、過去の成功体験や専門知識だけでは対応しきれない時代になっています。そうした中で、「誰かが指示を出し、他が従う」という旧来のスタイルは限界を迎えました。チームの中で多様な視点を出し合い、自律的に意思決定できる力がより重視されるようになっています。
(2)ハイブリッドワークと非対面コミュニケーションの拡大
オンライン会議やチャットでのやりとりが主流になると、表情や空気感が読みづらくなります。そこで重要になるのが、「相手の立場や感情を慮る想像力」や、「明確に、かつ丁寧に伝える表現力」といったソフトスキルです。デジタル時代だからこそ、人間的な関係性を構築するスキルがより重要視されているのです。
(3)生成AIと人間の役割の再定義
AIが急速に進化するなかで、「論理的な処理」や「データの蓄積と検索」といった分野はAIに任せられるようになりました。では人間にしかできないこととは何か? それがまさに、共感し合い、対話し、信頼を築くといったソフトスキルです。
Googleの人材開発部門「Project Oxygen」の調査によれば、最高のマネージャーに共通する資質の多くはソフトスキルに関係していたことが明らかになっています【引用:Google re:Work】。
ソフトスキルは、単に「感じがいい人」になるためのものではありません。組織の信頼を育て、チームを活性化させ、会議という場を価値あるものに変える根本的なスキル群なのです。
3.ソフトスキル不足がもたらす“会議の機能不全”
「この会議、何のためにやってるんだろう?」「誰も本音を言わない」「結局、決まらないまま終わった」
そんな会議に心当たりはないでしょうか?
これらはすべて、ソフトスキルの不足によって引き起こされる、典型的な“会議の機能不全”です。
3-1. 空気を読むばかりで、建設的な意見が出ない
日本の会議では「和を乱さない」ことが重視される傾向が強く、本音や異論を口にすることがはばかられる場面が多く見られます。しかしこれは、心理的安全性が欠如している状態を意味します。
本来、会議は意思決定や知恵の融合の場であるべきです。けれど、相手の反応を過剰に気にするあまり、誰も率直な意見を出せなくなってしまう。これは「共感力」「フィードバックスキル」「傾聴力」などのソフトスキルが育っていない証拠です。
その結果、会議は単なる報告会と化し、形骸化していきます。
3-2. 発言が偏る、“一部の人だけ”の会議になる
ソフトスキルが不足すると、会議内の発言の偏りが顕著になります。
上司ばかりが話し、部下はうなずくだけ。あるいは、話すのが得意な数人に場を握られてしまい、他のメンバーは“いてもいなくても変わらない”状態になる。
これは、「対話を引き出すスキル」や「フォロワーシップ」、「場づくり力」の欠如によるものです。
組織内でこのような会議が常態化すると、メンバーの関与意識は低下し、“自分ごと”ではなく“他人ごと”として仕事に向き合う風土が形成されてしまいます。
3-3. 問題解決ではなく、責任回避が目的になってしまう
ソフトスキルが未熟な組織では、会議の場においても“防衛的な発言”が増える傾向にあります。
・「私は言いました」
・「前から課題だとは思っていました」
といった、責任を回避する言い方が目立つようになると、それはもう「創造の場」ではなく、「自己防衛の場」です。
これは、感情マネジメントの未熟さや、信頼の土壌が築かれていないことに起因します。
本来、会議は未来に向けて課題を共有し、行動に落とし込むための場。しかし、ソフトスキルが育っていないと、過去への言い訳や責任の所在をぼかす発言ばかりが続き、前向きな議論ができなくなります。
小さな“ひずみ”が、組織全体の歪みに変わる
このように、ソフトスキルの不足が引き起こすのは「些細な違和感」かもしれません。
しかしそれはやがて、会議の質を低下させ、意思決定を曖昧にし、行動変容を妨げる大きな障害となります。
そして、それはチームの成果やモチベーションにまで波及していくのです。
4.会議を機能させるためのソフトスキル5選
会議の質は、参加者一人ひとりの「関わり方」によって決まります。そして、その関わり方を支えるのがソフトスキルです。ここでは、特に会議を「機能させる」ために必要な5つのソフトスキルを紹介します。
4-1. 傾聴力:相手の意図を正しく受け取る
傾聴とは、単に「聞く」ことではありません。
相手の背景・意図・感情を汲み取ろうとする姿勢があって初めて、傾聴は成立します。
たとえば、あるメンバーが意見を述べたとき、途中で遮られたり、顔色で否定されたように感じれば、その人は次から発言しなくなるでしょう。
傾聴力は、心理的安全性の土台を築き、会議を「対話の場」に変えるための最初のステップです。
4-2. 質問力:沈黙を打破し、議論を前に進める
「誰も話さなくなる瞬間」を経験したことがある方も多いのではないでしょうか?
そんな時こそ求められるのが、問いを立てる力です。
「どう思う?」「なぜそう感じた?」といったシンプルな問いでも、会議の空気は大きく変わります。
質問は“意見を引き出す装置”です。答えを急がず、思考を深める問いを投げかけることで、会議に参加する全員の視野が広がっていきます。
4-3. 共感力:発言の背後にある想いや不安に気づく
会議では、事実や意見だけでなく、感情も飛び交っています。
たとえば、「このままではまずいと思うんです」という言葉には、不安や焦り、責任感が含まれているかもしれません。
こうした感情の機微に敏感になることは、対立を回避し、前向きな議論へとつなげるうえで欠かせません。
共感は、場の雰囲気をやわらげる潤滑油です。共感的なリアクションがあるだけで、参加者は「この場で話していいんだ」と感じるようになります。
4-4. フォロワーシップ:支えることで議論を育てる
リーダーシップばかりが注目されがちですが、会議を支える“影の主役”はフォロワーシップです。
誰かの発言に「それ、面白いですね」「もう少し詳しく聞かせてください」と前向きに乗っかる力は、会議の熱量を高め、議論を広げてくれます。
一歩引いて場を俯瞰したり、発言しづらい人に声をかけたりする姿勢も、重要なフォロワーシップです。会議の成功は、こうした小さな関与の積み重ねに支えられているのです。
4-5. 自己開示力:会議を“安全な場”に変える
最後に、実は最も重要なのが「自己開示」です。
自分の考えや弱みを先にさらけ出すことで、周囲も自然と心を開きやすくなります。
たとえば、「実は私も迷っていて……」というひと言が、会議全体の緊張をほぐし、率直な対話のきっかけになることがあります。
自己開示は、“弱さ”ではなく“信頼”の表現です。
ソフトスキルが、会議の未来を変える
これらのスキルは、特別な技術ではありません。
日々の仕事の中で少しずつ育てていくことができる“力”です。
そして、ソフトスキルが自然に発揮されるようになったとき、会議は単なる業務の場から、組織を進化させる原動力へと変わります。
5.ソフトスキルは“研修だけ”では育たない
「ソフトスキルを強化するには、まず研修を」と考える方は少なくありません。
たしかに、研修はスタート地点として有効です。しかし、研修“だけ”でソフトスキルが育つことはありません。
なぜなら、ソフトスキルとは“知識”ではなく“習慣”であり、“感覚”であり、“態度”だからです。
一度学んだだけでは、会議というリアルな場で自然に発揮できるレベルには至りません。
5-1. 知っている ≠ できている
研修で「傾聴の重要性」を学んでも、実際の会議で部下の話を最後まで聞かずに口をはさんでしまう──
こうしたギャップは多くの現場で見られます。
これは、ソフトスキルが反射的な行動に表れる性質を持っているからです。
習慣化されていないスキルは、緊張や焦りのなかで、すぐに“元の自分”に戻ってしまいます。
5-2. 実践とフィードバックのループが必要
ソフトスキルを本当に自分のものにするためには、「実践 → フィードバック →再実践」のループが不可欠です。
たとえば、会議の中で実際に「質問力」を意識して使ってみる。その後、同僚やファシリテーターから「こんなふうに問い直すともっと深まるかも」といったフィードバックをもらう。さらに、次の会議でそれを試してみる──こうしたサイクルがスキルを定着させます。
5-3. 「日常」が最大のトレーニングの場
ソフトスキルは、実は日常のなかにこそ成長のチャンスがあります。
毎日の会議、1on1、雑談、プロジェクト進行中のやり取り──
これらすべてが“実践の場”です。
つまり、研修を受けた後に、どんな行動を継続できるかがすべてです。
研修はあくまで「スイッチを入れる装置」。
それを継続的に“回し続ける”仕組みがなければ、効果は持続しません。
5-4. 組織に求められる「育成のデザイン」
ソフトスキル育成の本質は、個人だけに責任を押しつけないことです。
「学んできたんだから、あとは自分で頑張って」では定着しません。
- 会議後にフィードバックの時間を設ける
- ソフトスキルの実践を振り返る仕組みをつくる
- 上司も一緒に“育成の主役”として関わる
こうした育成を組織的に支える「文化と設計」が必要なのです。
5-5. ファシリテーターによる伴走の効果
実践とフィードバックを支える存在として、ファシリテーターの伴走は非常に有効です。
第三者だからこそ言えること、指摘できること、拾える感情があります。
「会議がうまくいかない原因は何か?」
「参加者の関わり方にどんな傾向があるか?」
こうした“見えにくい構造”を言語化し、チームの内省をサポートすることが可能です。
ソフトスキルは「場づくり」と「継続」で育つ
ソフトスキルは、単発の研修では育ちません。
育つのは、日々の会議・対話・失敗と学びを繰り返す“実践の場”においてです。
そのためには、育成の仕組みをつくる側にも視点を向ける必要があります。
“育つ場をいかに設計するか”こそが、会議を変え、組織を変える本質なのです。
6.aundのアプローチ:ソフトスキルで会議と組織を変える
ソフトスキルは、もはや「持っていたら嬉しいスキル」ではなく、チームや組織を動かす“根幹”の力です。
しかし、実際の職場では「どう育てるか」「どう評価するか」「どう現場に落とし込むか」が曖昧なまま放置されがちです。
aundでは、こうした“育ちにくいスキル”を 育つ環境に変えていく実践支援を行っています。
6-1. ファシリテーションで「学びを定着させる場」をつくる
単なる講義型の研修では、ソフトスキルは浸透しません。
aundのアプローチは、会議そのものを「学びの場」に変えることにあります。
たとえば、
- 何が会議の「質」を下げているのかを参加者と一緒に振り返る
- 会議中にリアルタイムでの“関わり方”に着目する
- ファシリテーターがその場でフィードバックを挟み、行動を言語化する
といったプロセスを通じて、参加者自身が「どんなソフトスキルを持ち、何を変える必要があるか」を自分ごととして捉えられるようになります。
6-2. 会議ファシリテーション×チームビルディングの設計
aundでは、ソフトスキル強化の文脈で以下のサービスを提供しています:
- 会議ファシリテーション支援
組織内の重要な会議に第三者として参加し、構造化・可視化・議論の推進を行います。 - ソフトスキル強化型ワークショップ
傾聴、対話、質問力、リフレクションなどを、実践とセットで体得する半日~1日のセッションを設計可能です。 - チーム伴走型プログラム
3~6か月間、チームに継続的に伴走し、会議における各スキルの定着と組織としての行動変容を促進します。
これにより、「研修で学んで終わり」ではなく、現場の行動が変わるところまでを徹底して支援します。
6-3. 「ソフトスキルから組織を変える」ために必要なこと
会議におけるソフトスキルの向上は、単なる“会議術”にとどまりません。
これは、組織文化のアップデートそのものでもあります。
- 発言しやすい文化
- 意見が尊重される環境
- 職位を越えたフラットな対話
- 自他の違いを受容する関係性
こうした土壌があってこそ、戦略も施策も機能しはじめます。
6-4. ソフトスキルは「組織の未来を変える投資」
今、多くの企業が「人が辞める」「会議が空回りする」「部門間が分断している」といった課題を抱えています。
その根本にあるのは、“関わり方の質”への無自覚です。
aundは、ソフトスキルを“個人のスキル”ではなく、組織の競争力そのものと捉え、
「会議の変革」から「組織の変革」へとつなげていきます。